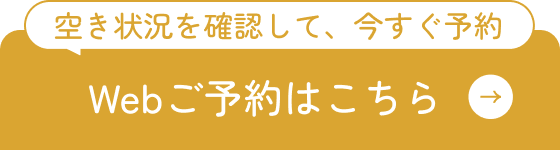低用量ピル

避妊や生理痛、PMSなど幅広いお悩みに対応した低用量ピルの仕組みや効果、副作用、服用方法などを解説しています。川崎市にある当院五十嵐レディースクリニックでは、専門医が丁寧にご相談をお受けしています。
こんなお悩みの方は
ご相談ください
- 年々ひどくなる生理痛の原因を知りたい
- 受験や就職試験までに、生理痛を治したい
- 生理前になるとイライラしたり落ち込んだりする
- 女性ホルモンや低用量ピルなどを専門にするかかりつけ医を持ちたい
- 生理が不順で体調が悪くなる
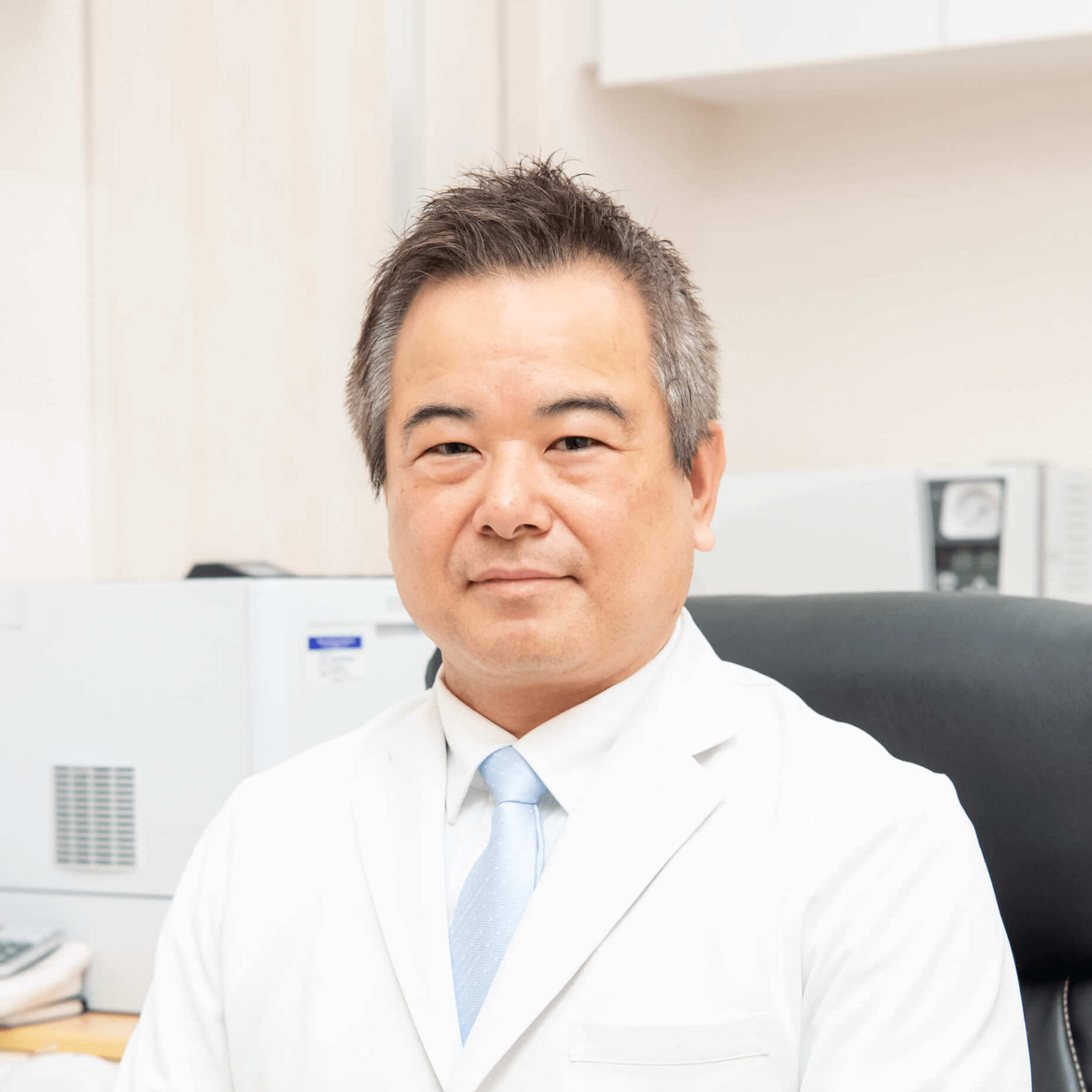
日本産科婦人科学会専門医・女性ヘルスケア専門医として産婦人科医療に長年携わり、聖マリアンナ医科大学産婦人科学の臨床教授も務めています。現在は医療法人寬繋会 五十嵐レディースクリニック理事長として、地域の女性医療に力を注いでいます。
低用量ピルとは

OC(Oral Contraceptive)
1999年に日本で初めて承認された避妊用ピル。
避妊目的で処方されるピルで、主にアンジュ🄬、トリキュラー🄬、マーベロン🄬、ラベルフィーユ🄬、ファボワール🄬などの製品があります。
OCは病院・クリニック・オンライン診療などで処方され、費用は1か月あたり約3,000円が目安です。
LEP(Low dose Estrogen-Progestin)
2008年に月経困難症(月経痛)の治療薬として保険適用になったピル。
LEPは、子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症による月経痛の治療に保険で処方されるほか、原因不明の生理痛に対しても適用されます。先発品とジェネリック医薬品があり、価格は製品によって異なります。
代表的な製品にはヤーズ🄬、ヤーズフレックス🄬、ドロエチ🄬、フリウェル🄬などがあり、それぞれ効果や服用方法に違いがあります。
なお、これらの低用量ピル(OC・LEP)は、継続的な服用によって効果を発揮するため、月経移動に使用される中用量ピルや、緊急避妊(アフターピル)として使用されるピルとは使用目的・方法が異なります。
仕組み

排卵が起こらないため、妊娠が成立しにくくなる=避妊効果が得られるという仕組みです。
正しく服用した場合、使用開始から1年間の避妊失敗率(妊娠率)はわずか0.3%とされており、非常に高い避妊効果が期待できます。
効果

低用量ピルを使用することで得られる効果は主に以下の5つです。
- 避妊
- 生理痛の軽減
- 生理周期の改善
- 月経前症候群(PMS)の改善
- 卵巣がん・子宮体がんの予防(リスク軽減)
避妊
低用量ピルは、排卵を抑えることで妊娠を防ぐ仕組みです。脳から分泌されるホルモンの働きをコントロールし、卵子が排卵されないようにすることで、高い避妊効果を発揮します。 日本国内の臨床試験では、正しく服用した場合の妊娠率(パール指数)は0〜0.59と報告されており、避妊手術やIUD(子宮内避妊器具)と同等レベルの高い効果が認められています。コンドームやリズム法よりも確実性が高く、日常的に取り入れやすい点も大きなメリットです。 さらに、長期服用しても死亡率に変化がない、あるいは低下するという報告もあり、安全性についても一定の信頼性が確認されています。
生理痛の軽減
低用量ピルは、排卵を抑えることで子宮内膜の増殖を抑制し、生理中に分泌される痛みの原因物質「プロスタグランジン」の生成を減らします。そのため、生理痛がやわらぎ、月経量の減少も期待できます。また、子宮内膜症のある方では、内膜症に伴う卵巣腫瘍の縮小や腹痛・腰痛の軽減にもつながります。加えて、ニキビの改善や、PMS(月経前症候群)・PMDD(月経前不快気分障害)などの症状緩和にも有効とされており、海外では治療の第一選択とされるケースもあります。さらに、卵巣がんや子宮体がん、大腸がんのリスクを低下させることがわかっており、避妊以外にも多くの健康上のメリットがある薬です。
生理周期の改善
生理周期が整っていないと感じる方にとって、低用量ピルは妊娠を防ぎながら規則的な月経周期をつくるのに役立ちます。ただし、正常な生理周期とは25日〜38日間隔であり、その周期の変動が6日以内であると定義されています。この範囲に当てはまっていれば、特別な治療は必要ない場合もあります。一方で、周期がこの範囲から外れている場合は、まずその原因となる病気がないかどうかを確認することが大切です。生理不順の背景には、やせすぎや肥満、脳腫瘍、高プロラクチン血症、甲状腺の異常、早発卵巣不全、多嚢胞性卵巣症候群、糖尿病など、さまざまな疾患が関係している可能性があります。気になる場合は、まず専門の産婦人科を受診しましょう。
月経前症候群(PMS)の改善
月経前症候群(PMS)は、月経が始まる3〜10日前から心や体にさまざまな不調が現れ、月経が始まると自然に軽くなるのが特徴です。原因はまだはっきりとは解明されていませんが、精神的な落ち込みやイライラ、むくみ、乳房の張りなどで日常生活に支障をきたすこともあります。日本では主に生活指導や漢方薬による治療が行われてきましたが、海外では抗うつ薬の一種であるSSRIがPMSの第一選択薬とされている国もあります。ただし、SSRIは日本では保険適用外であり、「うつ病の薬」というイメージから敬遠されることも少なくありません。
そのような背景の中で、低用量ピルの一種である「ドロスピレノン配合ピル」が注目されています。このピルにはホルモンバランスの乱れによる症状をやわらげる作用があり、むくみや気分の落ち込み、乳房の痛みなどを改善する効果が期待できます。日本でも「ヤーズ配合錠®」や「ヤーズフレックス配合錠®」、ジェネリックの「ドロエチ配合錠®」が使用されており、特に連続して服用する「ヤーズフレックス配合錠®」の方が効果が高いとされています。現在のところPMSに対しての保険適用はありませんが、月経困難症の治療の一環として処方されることがあります。PMSの症状がつらい方は、低用量ピルという選択肢も一度検討してみてください。
卵巣がん・子宮体がんの予防(リスク軽減)
低用量ピルには、避妊以外にも「がんのリスクを下げる」という重要な効果があります。とくに卵巣がんと子宮体がんについては、その予防効果が医学的に明らかになっています。
卵巣がんは、遺伝的な要因のほかに、排卵や性腺刺激ホルモンの影響が発症に関係するとされており、低用量ピルの服用によって排卵が抑えられることでリスクを減らせると考えられています。実際に、服用により卵巣がんの発症リスクは25~33%低下し、BRCA1やBRCA2といった遺伝性乳がん・卵巣がんに関係する遺伝子を持つ方でも、その効果が確認されています。さらに服用期間が長いほど予防効果は高く、服用をやめた後も約10年間はその効果が続くことがわかっています。
また、低用量ピルは子宮体がんの予防にも効果があります。これは、ピルに含まれる黄体ホルモンが子宮内膜の過剰な増殖を抑えるためと考えられており、子宮体がんの発症リスクを22~43%も下げるという報告があります。加えて、死亡率の低下も確認されており、服用期間が長いほど効果は高く、服用終了後約20年が経過してもリスク低下の効果が持続することが示されています。
副作用

吐き気、頭痛、めまい、乳房緊満感、不正出血
有名なマイナートラブル。ホルモンバランスの変化によるもので多くは自然によくなります。改善を認めない、または悪化する場合はその低用量ピルが体に合わない場合があるのでご相談ください。
静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism : VTE)
米国の調査によると、生殖可能年齢女性の発症頻度は1万人に1~5人であるのに対して、低用量ピルを使用すると3~9人と2倍に増加することが報告されています。しかしながら、妊娠中の女性の発症頻度は5~20人、産後3か月まででは40~65人とさらに高いため、妊娠中よりも低いことがわかります。さらに、日本国内での調査では低用量ピル使用中の発症頻度は1万人に1人と欧米より低いことが報告されています。しかしながら、肥満と喫煙、年齢によって低用量ピルの使用は静脈血栓塞栓症のリスクを増加させます。35歳以上で1日にたばこを15本以上吸われる方、50歳以上あるいは閉経後の方は静脈血栓塞栓症のリスクが高いので低用量ピルの使用が禁止されています。また、BMI(Body mass index: 体重㎏÷身長m÷身長m)が25を超えるとその値の上昇に伴いリスクが増大します。
異常子宮出血
低用量ピルを使用した20%の方が経験するといわれていますが、継続して使用することによって減少します。
精神的に不安定になる・体重増加
低用量ピルのガイドラインでは使用により増加しないと記載がありますが、私の経験上一定数いらっしゃるので、その際は薬のメーカーや種類の変更を提案させて頂いています。
子宮頸がん・乳がん
低用量ピルの使用によって増加する可能性があると記載されている文献が多いです。当院では性交渉の経験のある方は子宮頸がん検査を毎年提案しています。また、乳がんに関しては、日本では10人に1人は乳がんに罹患するといわれていますので、40歳を超えていなくても定期的な乳がん検査を推奨しています。残念ながら当院は乳がん検査ができませんので、近隣の病院に検査を依頼し結果を当院で説明する形をとっています。
服用までの流れ

受付(問診表の記入)
当院五十嵐レディースクリニックで低用量ピルをご希望の場合、まずは問診票のご記入をお願いしています。
避妊が目的か、生理痛の改善など治療が目的か、これまでにかかった病気や治療中の病気、現在服用中のお薬、ご家族の病歴、ご年齢やご職業などについてご記入いただきます。その後、毎回の処方時に血圧と体重の測定を行います。
診察
診察では、問診票の内容を医師が確認し、子宮や卵巣の状態を把握するために超音波検査を行います。
月経痛の原因となる病気の有無を確認するため、また避妊目的の方でも見逃されがちな疾患の早期発見を目的としています。通常は経腟超音波で検査を行いますが、性交経験のない方には経肛門的な検査を提案させていただいております(ただし、ご希望されない場合は無理に実施いたしません)。
診断が目的ではなく、あくまで月経に伴う不調を改善し快適な日常をサポートすることが目的ですので、ご安心ください。
薬の処方
低用量ピルにはいくつかの種類があり、症状やご希望の価格、体質に合わせて、必要に応じて他の治療薬も含めながら相談のうえ選択します。はじめて使用される方には、体との相性を確認するために、まず1か月分から処方しております。
低用量ピルを服用できない方
リスクとベネフィットの観点から、以下にお示しした患者さんには低用量ピルを処方しない、原則処方してはいけない、と定められています。
- アレルギーなど、服用により不都合な症状が出たことがある方
- 現在または過去に乳がんに罹患したことがある方
- 原因不明の不正出血がある方(がんの可能性があるため)
- 血栓症や心筋梗塞、脳卒中の既往がある方、または抗凝固療法中の方
- 35歳以上で1日15本以上の喫煙をする方
- 前兆を伴う片頭痛がある方(視界がチカチカするなど)
- 心臓弁膜症がある方
- 網膜・腎障害を伴う糖尿病の方
- 血液が固まりやすい体質・家族歴がある方
- 抗リン脂質抗体症候群と診断された方
- 手術予定または長期入院中の方(血栓リスクが高まるため)
- 重度の肝機能障害や肝がんがある方
- 重度の高血圧の方
- 脂質異常症に加え、高齢・喫煙・高血圧・糖尿病などのリスクがある方
- 妊娠中に黄疸・全身のかゆみ・ヘルペスを経験したことがある方
- 妊娠中の方(胎児への安全性が未確認)
- 産後6か月未満で授乳中、または産後3週間未満の方
- 月経がまだ始まっていない女性(骨の成長を止める恐れがある)
- 50歳以上または閉経後の女性(静脈血栓症のリスクが高まる)
種類

低用量ピルは、エストロゲンとプロゲスチンという2種類の女性ホルモンを含んでおり、主に避妊や生理痛の軽減を目的として使用されます。その中でも、プロゲスチンの一種「ドロスピレノン」を配合したピル(ヤーズ🄬、ヤーズフレックス🄬、ドロエチ🄬)は、月経前の気分や体調の変化がつらい「月経前症候群(PMS)」や「月経前不快気分障害(PMDD)」にも効果があるとされています。実際に、ドロスピレノンを含む低用量ピルがPMS治療の第一選択とされている国もあります。
2024年12月には、新しいタイプのエストロゲン「エステトロール」とドロスピレノンを組み合わせた「アリッサ🄬」が登場しました。これまでよりも静脈血栓症のリスクを低減できる可能性があり、より安心して使える選択肢として注目されています。
また、低用量ピルには服用スケジュールに違いがあります。たとえば、21日間服用して出血を促すタイプ(ヤーズ🄬、ドロエチ🄬、フリウェル🄬、アリッサ🄬、アンジュ🄬、トリキュラー🄬、マーベロン🄬、ラベルフィーユ🄬、ファボワール🄬)と、出血がなければ継続的に服用できるタイプ(ヤーズフレックス🄬、ジェミーナ🄬)があります。連続投与型は、月経回数を減らして生理痛をより抑える効果がある一方、人によっては月1回程度の出血が起こることもあります。
どのタイプが自分に合っているかは、生活スタイルや症状に合わせて選ぶことが大切です。産婦人科で相談しながら、ご自身に合ったピルを選びましょう。
当院五十嵐レディースクリニックで処方している低用量ピル
低用量ピルを希望される理由が避妊なのか生理痛の治療なのかに関わらず、海外から輸入をするものでなければすべての低用量ピルが処方できます。院内処方として直接お渡しできるのはヤーズフレックス🄬、ドロエチ🄬、フリウェルLD(あすか)🄬です。
費用

一方、生理痛の治療として使用する場合は保険適応となります。院内処方として直接お渡しできるのはヤーズフレックス🄬、ドロエチ🄬、フリウェルLD(あすか)🄬ですが、1か月分の価格としてそれぞれおよそ2500円/月、900円/月、600円/月です。
保険診療で低用量ピルが処方される際には、子宮内膜症や子宮腺筋症、子宮筋腫など生理痛の原因がはっきりしている場合が多く3か月ごとに別途管理料がかかりますが、当院では避妊目的の料金より高くなることはありません。
当院での低用量ピルの受け取り方
避妊目的あるいは生理痛の治療を目的どちらの場合でも、内服できない疾患や状態、生活習慣がないかを確認します。そして身長を確認し、当院では毎回体重測定、血圧測定を行っております。
生理痛の治療を目的にされていらっしゃる方は、初診時に原因となる病気がなにかをはっきりさせるために内診や超音波の検査を行っております。そのあとに低用量ピルの種類を相談し処方致します。当院に在庫がある場合にはその場でお渡しできます。低用量ピルの内服による副作用を確認するため、処方時に毎回お話を伺い定期的に採血検査や子宮がん検診を行います。職場や人間ドックなどで定期的な採血検査等をなされてらっしゃる方は、その結果を拝見し代用させて頂くこともあります。
よくあるご質問
川崎市で低用量ピルのご相談は
五十嵐レディースクリニックへ

低用量ピルは避妊を希望される方や生理痛で毎月悩んで追われる方に対して、簡便手軽に、そして長期に使用しても安全です。高い避妊効果と生理痛を改善させることができるだけでなく、にきび(尋常性ざ瘡)を改善する効果もあります。また一部の低用量ピルはPMS(月経前症候群)やPMDD(月経全不快気分障害)などの月経前の多彩な症状に対して改善効果がある多くの利点を持つ薬剤です。
しかし一方で、服用中のトラブルや採血検査でしか見つけることのできない副作用も存在します。避妊を目的に、あるいは生理痛の原因を見つけ、当院五十嵐レディースクリニックで患者様それぞれに合った治療法を一緒に見つけていきましょう。
お問い合わせはこちらから
CONTACT
五十嵐レディースクリニックでは、
川崎市で避妊や生理痛、更年期症状など女性特有のお悩みを丁寧にサポートしています。どんな小さなことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談・ご予約ください。
お気軽にご相談ください
044-948-9100
空き状況を今すぐ確認
Webご予約はこちら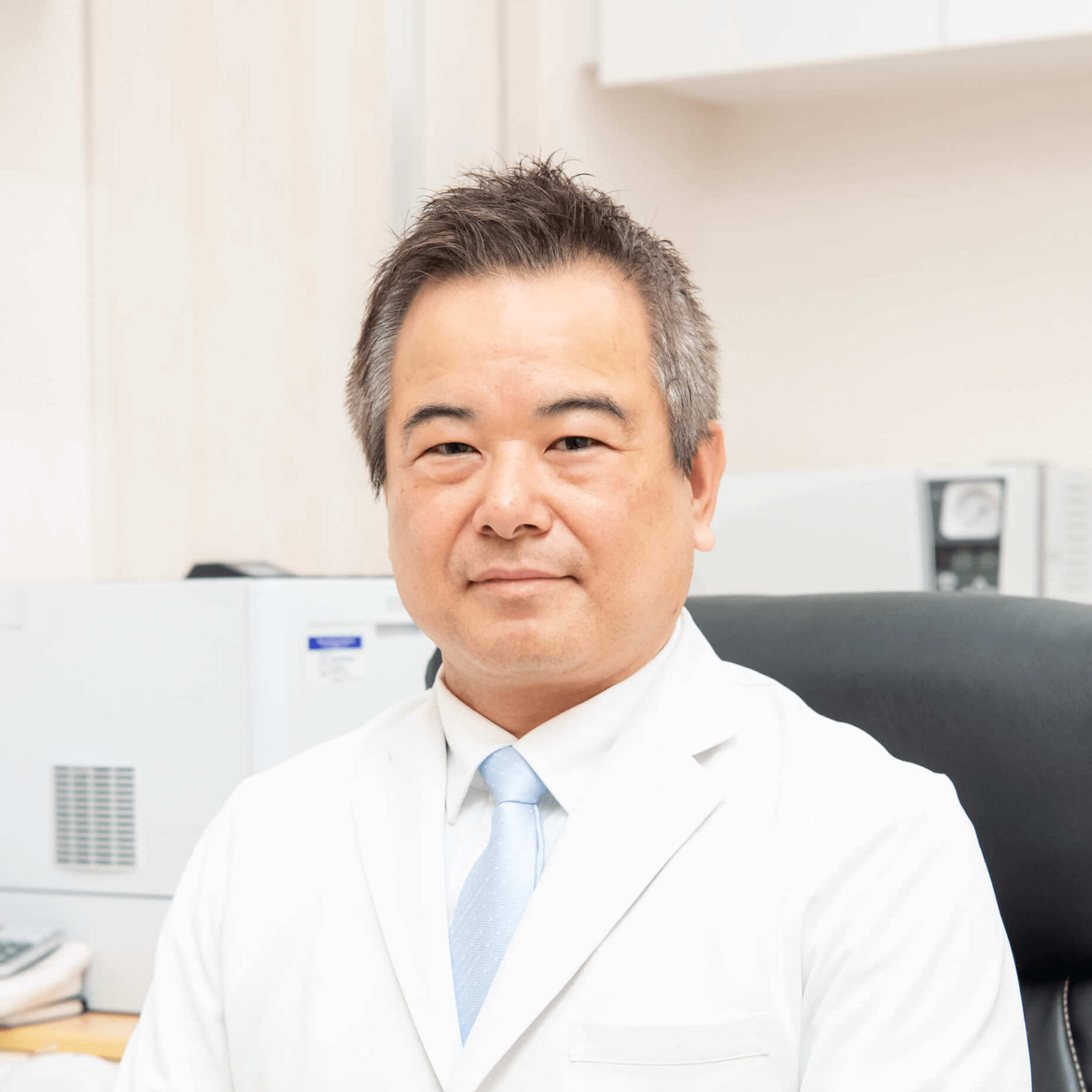
日本産科婦人科学会専門医・女性ヘルスケア専門医として産婦人科医療に長年携わり、聖マリアンナ医科大学産婦人科学の臨床教授も務めています。現在は医療法人寬繋会 五十嵐レディースクリニック理事長として、地域の女性医療に力を注いでいます。
詳しく見る